
脱プラスチックが叫ばれる中、日本企業の間では代替品の活用に注目が集まっています。そもそも脱プラスチックについて、改めて確認しておくことも必要ではないでしょうか。
今回は、脱プラスチックの概要やプラスチックによって起きている環境問題、脱プラスチックのメリット・デメリット、プラスチックを減らすための取り組みからプラスチック代替品・代替素材の種類までご紹介します。
目次
脱プラスチックは意味がない?

脱プラスチックとは、プラスチック製品の使用量を減らす取り組みを指します。近年、プラスチックは環境負荷が高いことが指摘され、これまでプラスチックに依存してきた状態を脱する意味合いから"脱"プラスチックと呼ばれています。
国内外で、プラスチックに代わる紙や木材、環境負荷の低いプラスチック製品などの使用が進む中、「脱プラスチックは意味がない」という声もあります。その背景として、個人がレジ袋を使用せず、マイバッグを持参する細々とした取り組みは、プラスチックが与える環境負荷を低減するなどの大きな成果にはつながりにくいと考えられている点などが挙げられます。
しかしながら、プラスチックによって起きている環境問題を知ると、意味がないように思える細かな行動でも、必要性を感じざるを得ないところがあります。
プラスチックごみの増加によって起きている環境問題

近年、プラスチックごみの増加に伴い、次のような環境問題が深刻化していることが指摘されています。
地球温暖化
プラスチックは生産時や処分時に二酸化炭素(以下、CO2)を排出し、さらには経年劣化の段階で温室効果ガスであるメタンを排出するといわれます。これらが日々、大量に排出されると、余分な熱が宇宙に排出されず、地球温暖化が進んでしまいます。プラスチックを生産すると、それだけで地球温暖化につながってしまうのです。
海洋汚染
プラスチックは自然界において微生物によって分解されないため、ごみとして適切な廃棄処理が必要です。しかしポイ捨てや処理されなかったプラスチックごみは自然界に残り続けます。特に海洋に流れ着いたものによる海洋汚染が深刻化しています。環境省が行った漂着ごみのモニタリング調査(平成28年)では、個数ベースではプラスチックは65%を超える割合となっています。想定される被害として生態系を含めた海洋環境への影響などがあり、問題視されています。
脱プラスチックのメリットとデメリット
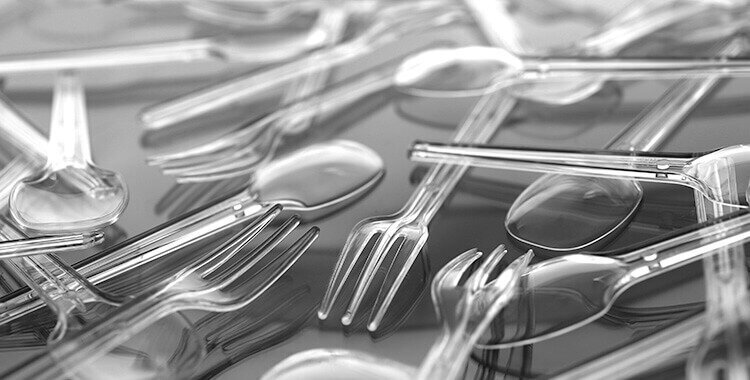
地球環境への影響を踏まえると、脱プラスチックには重要性を感じられます。ここで、企業が脱プラスチックに取り組む具体的なメリットを確認していきましょう。また、あわせてデメリットについてもご紹介します。
【メリット】
CO2の発生削減
東京都の統計では、都内の家庭や大規模オフィスビルから排出されるプラスチックは80万トンにも上り、そのうち約70万トンが焼却され、145万トンのCO2が発生していることがわかります。脱プラスチックに取り組むことで、CO2の発生の削減につながります。
「典型7公害」の改善
環境基本法では「典型7公害」として「大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下及び悪臭」の7種類の公害が定義されていますが、脱プラスチックを進めることにより、これらの改善に役立ちます。
製造業界の発展
脱プラスチックを進めることで、プラスチックに代わる新たな素材が普及したり、食品容器やストローなどがプラスチックから紙製品に移行されたりと、脱プラスチックによって、製造業界はこれまでとは異なる方向に発展すると考えられます。
【デメリット】
耐久性/防水性が低い
プラスチックに代わる材料へと転換が進む中、プラスチックの特長である耐久性や防水性を担保できる材料が限られる点が課題となっています。
透明包装や半透明包装が難しくなる
プラスチックは、透明や半透明を実現しやすい点もメリットでした。その点、代替素材について実現しにくい点は課題です。
こうした課題を受け、新たな素材開発が進められています。
プラスチックを減らすための取り組み

プラスチックを減らすために、日本政府や企業、個人それぞれが取り組みを進めています。ここでは具体的な例をご紹介します。
〈日本政府の主な取り組み〉
プラスチック資源循環戦略
2019年5月に環境省や経済産業省などの連名で策定された戦略です。プラスチックの生産量を減らす「リデュース」、容器包装や使用済みプラスチックを繰り返し使う「リユース・リサイクル」、再生利用・バイオマスプラスチックの導入などが目標として掲げられ、国を挙げて取り組みが行われています。
レジ袋有料化
2020年7月1日よりプラスチック製買い物袋(レジ袋)の有料化が始まりました。レジ袋が本当に必要かを一人一人が考え、ライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。
海岸漂着物処理推進法
2009年7月15日に公布・施行された「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」の通称です。海洋漂着物対策を総合的・効果的に推進するための基本方針を通じて、円滑な処理や発生抑制のための施策が進められています。
〈企業の取り組み例〉
スターバックスコーヒージャパン株式会社
従来のプラスチックカップを使用していた一部のドリンクを、樹脂製グラスに入れて提供することで、使い捨てを削減する取り組みを行っています。
ライオン株式会社
掃除用洗剤などのつめかえパックには、プラスチックを利用していますが、複合素材から成ることで、容器としてリサイクルすることが難しいのが実情でした。そこでリサイクル性を向上させたつめかえパックを製品化し、脱プラスチックに貢献しています。
パッケージや梱包材の見直し・紙素材利用の工夫
多くの企業の事例です。商品パッケージや梱包材はジャンルを問わず、製品化や輸送の際に必要ですが、それらの素材を見直し、紙を利用することは第一選択肢となっています。さらに紙素材は再生紙や森林認証紙の利用により、有効活用されています。
再生紙(段ボール)の利用
再生紙は紙資源の有効活用につながると共に、特に再生紙の一種である段ボールは梱包材として有効活用されています。段ボールはリサイクルシステムが確立されていること、ライフサイクルを通じてCO2の排出量が少ないのが特徴です。
〈個人の主な取り組み〉
使い捨てプラスチックの削減
レジ袋の代わりにマイバッグ持参、コーヒーをカフェで注文するときに使い捨てカップではなくマイボトルに入れてもらうなどすれば、使い捨てプラスチックの削減につながります。
適切な分別とリサイクル
家庭ごみとして出るプラスチックごみは、できるだけリサイクルするために正しい分別を心がけることが有効といえます。
環境に配慮した消費行動
先述の脱プラスチック容器の商品を積極的に購入するなど、環境配慮の消費行動も有効です。
プラスチック代替品・代替素材の種類

プラスチック代替品・代替素材の種類をご紹介します。
段ボール
段ボールは、自然に還る紙素材であることから環境負荷が低く、国内ではリサイクルシステムが確立されている環境面で優秀な素材です。また加工のしやすさもメリットであり、使用面積を削減する工夫をすることで、より環境に優しく、コスト削減にもつながります。
バイオマスプラスチック・植物由来素材
バイオマスプラスチックとは、トウモロコシやサトウキビなどの植物を利用した再生可能な資源を原料にした、環境負荷が低減されたプラスチックです。植物は成長過程でCO2を吸収することから、廃棄物の焼却時に排出されるCO2は実質、地球上のCO2濃度を増やさない「カーボンニュートラル」な素材です。
生分解性プラスチック
生分解性プラスチックとは自然界で分解されるように開発された環境負荷の低いプラスチックです。ただし、分解には長い期間がかかることから、化学物質が微量に放出される可能性があります。
木材・紙
廃棄された後、自然に還る木材・紙は脱プラスチックの筆頭に上ります。近年、透明性のある木材が開発されるなど、今後はさらなる発展が期待されています。
まとめ

脱プラスチックの概要からメリット・デメリット、具体的な取り組み、代替素材をご紹介しました。
世界的にプラスチック規制が高まる中、日本国内でもさらに対応を強化する必要があるでしょう。
このような背景から、プラスチックの代替素材として優秀な段ボールの利活用を進めることは有効です。日頃、利用しているパレットや梱包材、緩衝材を段ボールに変換することも検討してみてはいかがでしょうか。
日本トーカンパッケージでは、プラスチック梱包に代わる加工技術「CFG(Cushion Flexible Gluer)」による梱包材や段ボールパレットを取り扱っております。CFGは内容物に合った成形が可能であり、段ボールシートを積層状にすることで、耐久性や強度を向上させることができます。
段ボールパレットについては、プラスチック製パレットで課題となっていた、輸出先で産業廃棄物処理になるなどのデメリットが段ボール製のワンウェイパレットで解決するメリットが一つに挙げられます。他にもリサイクルシステムが確立されていることで、使用後も再利用が可能なメリットもあります。このリサイクルプロセスにより、資源の無駄を最小限に抑え、持続可能な社会の実現に貢献します。
プラスチックの代替として段ボールをご検討されている場合、段ボールの形状や加工のご提案ができますのでぜひお気軽にお問合せください。






